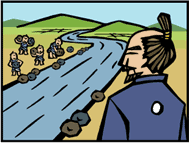甲佐町の民話・鵜の瀬ぜき(うのせぜき)
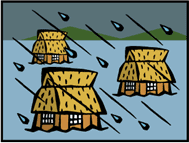
むかし、甲佐には、町の東と西に二つの川が流れていました。川には、堤防がありませんでしたので、雨がふると、たびたび洪水がおこり、農家の人びとは大へん困っていました。
そのころの、おとのさまは、加藤清正公でした。
清正公は、二つの川の流れを一つにして、ていぼうやせきを作ったら、こう水がおこらないようになり、田んぼにも水を流すことができるようになるだろうと、考えられました。 こうして、何千人もの人たちによって、工事が、始められました。
清正公も家来の人たちといっしょに、川に来て、工事のさしずをされました。山から、大きな石や木が切り出され、掛け声も高らかに運ばれてきました。五人力、八人力という力じまんの人たちでなければ運べないような大きな石が運ばれて、川につみ上げられました。この工事は、何年も、何年もかかる大へんなしごとでした。そのなかでも、もっともむずかしいのははげしい川の流れの中に、せきを作ることでした。
いろいろと、くふうをこらして、何回となくせきが作られましたが、はげしい水の流れにすぐ流されます。水の流れに勝つためのせきを作ることは、なかなか、できませんでした。そこで、清正公は、甲佐神社の神さまに、「工事が成功しますように、水に流されないせきを作ることが出来ますように。」と、何日も、何日も祈りつづけました。
ある夜のことです。清正公は、川のこちらの岸から、向こうの岸へ、ななめに鵜の鳥が並んでいる夢を見ました。
きらきらと、お日さまの光にかがやく、静かな川の水の上に、鵜の鳥が、きれいに並んでいます。
清正公は、夢からさめると、「これはきっと、神様のお告にちがいない。」と夜の明けるのを待って、馬をとばして行って見ると、鵜の鳥が何十ぱとなく、朝もやのたつ川の中に並んでいました。そこで、清正公は、鵜の鳥が並んでいたとおりに、せきを作らせました。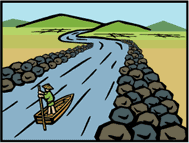
ところが、どうでしょう。せきは、はげしい水にも流されないようになりました。そうして、二つの川は、一つの川になり、長く、長く作られたていぼうにそって流れるようになりました。
これまで川の底だったところには、何百ヘクタールという広い田んぼが作られるようになりました。
これから、このせきは、『鵜の瀬ぜき』と呼ばれるようになりました。
カテゴリ内 他の記事
- 2025年7月4日 甲佐町へのアクセス
- 2022年5月23日 ご意見・お問い合わせ
- 2022年5月23日 甲佐町のご紹介
- 2016年2月22日 甲佐町の民話・猿王堂(さるおうどう)