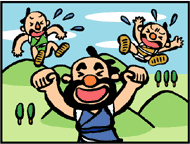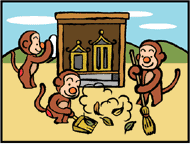甲佐町の民話・猿王堂(さるおうどう)
むかしむかし、まだ緑川が二つにわかれ、龍野の下と乙女の下を流れていたころのお話です。
乙女村に、金八という力の強い男が住んでいました。
あまり力が強いので、だれもかなうものがいませんでした。
金八は、たくさんのけらいをしたがえて、龍野や白旗の方まで出かけて乱暴をしましたので、近くの村人たちはとても困っていました。
そこで、村人たちはこのあたりをおさめている阿蘇の大宮司に、金八をこらしめてくださいとお願いしました。願いを聞いた大宮司は、すぐたくさんのぐんぜいをつかわしました。
阿蘇のぐんぜいが、緑川のほとりまで来てみると、水かさも多く、渡る橋もありません。そこで、川をおよいで向こう岸に渡ることにしました。
ところがどうでしょう。
川の中ほどまでくると、足を引っ張ったり、きものを引っ張ったりして、川の中に引きずりこまれてしまいます。
実は、川の中には、金八の手下のカッパたちがまちかまえていたのです。阿蘇のぐんぜいはたくさんおぼれたり、岸まで引き返したりしてしまいました。またつぎのぐんぜいを川にいれましたが、やはりおんなじで、なんどくりかえしても、向こう岸までたどりつくことはできませんでした。
大宮司はどうしたらよいかみんなにたずねました。
するとさるの王が、 『甲佐岳に住むさるたちをつかってください。』といいました。大宮司は、さるにたすけをたのむことにしました。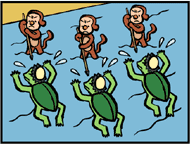
さるの王は、甲佐岳に住むさるたちをあつめて、
『阿蘇の神様のためにみんながんばってほしい』とたのみ、龍野の砂溜あたりにあつめました。
何万というさるが命令が出るのを待ちました。そのうしろには阿蘇のぐんぜいがならんでいます。
一方、向こう岸には金八のぐんぜいがあつまっています。川の中には、カッパたちが息をこらしてまっています。
どちらからともなく、ほら貝がたからかになりひびきました。
砂溜の方から、さるたちがいっせいに水に飛び込みました。
そしてカッパたちとはげしいたたかいがはじまりました。
どれくらいたったでしょうか。緑川はカッパとさるの死体でうずまりました。そしてとうとうさるがカッパをおいちらしてしまいました。このときをまっていた阿蘇のぐんぜいたちは、先をあらそって水に飛び込み、川を渡って金八のぐんぜいと戦いました。そのうち、数の多い阿蘇軍は、金八の軍をおいちらして、とうとう金八をとらえて首を切りました。
こうして、らんぼうをするものもいなくなり、平和な村がかえってきました。
このときのたたかいで、カッパやさるの死体が、万が瀬というところに何万も打ち上げられました。またさるの王も浅井の浅瀬死体になって打ち上げられました。村人たちは、さるの王のおかげで勝てたことに感謝して、さるの王のためにお堂をつくり、ねんごろにとむらいました。
これが猿王堂です。
猿王堂のおまつりは、九月十五日ですが、むかしは、九月の十三日ごろになると、甲佐岳からさるがおりてきて、猿王堂のそうじをしたそうです。
いっぽう、首を切られて死んだ金八も、このままではあまりにかわいそうだと、麻生原の人々がこっそり首をとりかえし、小さな塚を作り水神さんとしてまつりました。これが『金八水神』のおこりです。
麻生原の人々は毎年七月一日『金八さん祭り』をして金八のたましいをなぐさめました。これからは、麻生原の村からは、水におぼれて死ぬものがいなくなりました。それは金八のけらいだったカッパたちが、村の人たちをまもってくれるからだそうです。
カテゴリ内 他の記事
- 2025年7月4日 甲佐町へのアクセス
- 2022年5月23日 ご意見・お問い合わせ
- 2022年5月23日 甲佐町のご紹介
- 2016年2月22日 甲佐町の民話・鵜の瀬ぜき(うのせぜき)