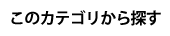H29.3月号 甲佐町の文化財探訪 「桶作りの技術」
更新日:2017年2月8日
桶が私たちの身の回りから消えて久しい。昭和28年頃までは、顔を洗ったり洗濯したり、ご飯や醤油を蓄えるのにも桶を使っていた。
しかし、科学技術の発達により、安価なアルミやプラスチック等の品が桶に代わって生活を支えるようになった。
桶はどのようにして作られたのか。衰退した今、その技術を文化の一面として記録に残しておくことは、大切な意味を持っていると思う。
昭和27年頃まで桶作りを専門とされていた小鹿の井上英一さんに、その技術を尋ねた。
桶が出来上がるまで(直径1尺の場合)
(1) 曲がった鉈で丸太を柾目状に割り、素材を作る。
(2) コンパスで直径1尺用のカマ(※1)を作る。(3) 素材の一枚一枚をカマに合わせて削る。内面はセン(※2)で、外面はカンナで削る。
(4) ご飯を潰しノリ状にして、削った板をつなぎ合わせ桶の原型を作る。
(5) 細い竹で輪を作り、桶を強く絞める。
(6) 底板をつけて完成。
桶作りを支えたのは、技術と同時に沢山の道具であった。底板を取り付ける為の道具や局面を削る道具など、工程に応じた道具が考案されていた。
※1 カマ…局面の大きさ、接続面の角度を決めるもの
※2 セン…両手で持ち、刃先で局面を削る道具(写真参照)
(文責 町文化財保護委員 清村一男(下豊内区))
カテゴリ内 他の記事
- 2024年9月18日 Created a tourism PR video for Kosa Town...
- 2025年12月16日 『甲佐町の文化財 第三集』の一般販売について
- 2025年11月27日 甲佐町の文化財探訪「糸田の大綱引き」〜令和8年1月号
- 2025年11月13日 公有化後における史跡等の管理・活用計画について
- 2025年10月28日 国指定史跡「陣ノ内城跡」の御城印の販売を開始します。