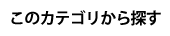宮内・甲佐地区 時代を映す、史跡巡りコース。
甲佐神社を起点に緑川沿いの名所・旧跡などをたどります。
甲佐神社
緑川が急峻な山間の地形を抜け、平野が広がり始める右岸の丘陵地に立つ甲佐神社は、阿蘇神社の摂社で、阿蘇神社、甲佐神社、健軍神社、郡浦神社を総称して阿蘇四ヶ社ともよばれます。祭神は、第一に甲佐明神、第二に阿蘇大神、第三に郡浦明神を祭ります。
十二世紀には阿蘇本社領の末社領となり、中世以降、「阿蘇家文書」にたびたび登場します。豊福荘生まれの豪族竹崎季長が元寇での奮戦を描かせた『蒙古襲来絵詞』は、この甲佐神社に奉納されたと伝えられます。
鳥居をくぐった参道の途中には、両脇に珍しい灯籠が現れます。向かって右側には灯籠を担ぐお相撲さん、左側には灯籠に乗る龍です。二つとも江戸時代に奉納されました。
所在地 甲佐町上揚
鵜ノ瀬堰
甲佐神社から500メートル程下流に位置する鵜ノ瀬堰は、加藤清正公によって1607年着手し翌年完成したと伝えられます。1メートル程に切りだした石を、全長660メートル、幅95メートルの範囲で、緑川を斜めに横断するように石畳状に敷き詰めています。
この鵜ノ瀬堰の築造については、加藤清正公にまつわる民話も残っています。
斜めに導かれた緑川の水は下流の「簗の樋門」を通り、大井手用水として約20キロメートルにわたり導かれます。甲佐、竜野、白旗、御船町豊秋地域の合計663ヘクタールの水田を潤し、江戸時代以降現在まで人々の生活を支えています。鵜ノ瀬堰は、その後の洪水被害により改修が繰り返され、一部は積み直されたり、一部はコンクリートになりましたが、左岸側に石畳の一部が確認できます。
所在地 甲佐町豊内 地先
簗の樋門
鵜ノ瀬堰の西、300メートル程下流に位置する簗の樋門は、加藤清正が鵜ノ瀬堰と同時に造ったものと考えられています。石材は、溶結凝灰岩を用いた切石で、アーチ部分のほか河床部分にも隙間なく敷き詰められています。アーチ部分の石材には、数字を刻んだものもあり、緻密な設計のもと作られたと思われます。
所在地 甲佐町豊内
緑川製糸場跡
緑川製糸場は、あゆのやな場の西に位置します。明治8年(1875)長野濬平の主導により嘉悦氏房を中心に操業を開始しました。群馬県富岡製糸場に次ぐ全国で2番目の器械製糸工場で、西日本で最初の、かつ最大の製糸工場でした。女工の多くは士族の娘で、嘉悦孝子(嘉悦氏房の娘、後に東京神田に女子商業学校を設立、女性の商業教育に力を入れた教育者)、徳富音羽(言論人徳富蘇峰、文学者徳富蘆花の姉にあたる)、兼坂きん(漢学者兼坂止水の娘)らがここで働きました。その後、原料繭の不足や経済不況により、明治15年(1882)休業しました。石碑の碑文は、徳富蘇峰によるものです。
所在地 甲佐町豊内
陣ノ内館跡
陣ノ内館跡は、町生涯学習センター東の小高い丘陵上にあります。北と東に400メートルになる堀を巡らし5メートルを越える土塁を併せ持つ城跡で、中世(鎌倉〜戦国期)に大きな力をもった豪族阿蘇大宮司の館跡と考えられていました。しかし最近の発掘調査によって南や西にも堀と土塁が巡らされていたこと、南東の土塁の切れ目を入り口にしていたことが分かり、その規模や形状から16世紀末から17世紀初めに作られた可能性が高いともいわれます。謎が多い城跡ですが、これほどの城を造ることができる当時の有力者というと、佐々成政、小西行長、加藤清正などが挙げられます。みなさんもぜひこの謎に挑戦してください。
所在地 甲佐町豊内
岩鼻神社
岩鼻神社は、県立甲佐高等学校の東、長楽山の一角にあります。2流を1流にまとめ堤防や堰を作った加藤清正公の緑川治水工事の偉業を後世に伝えようと寛永元年(1624)に建てられました。
所在地 甲佐町横田
新井手用水
岩鼻神社に登る中腹には新井手と呼ばれる用水があります。用水の開削は江戸時代の惣庄屋木原寿八郎の手により行われました。用水は、鵜ノ瀬堰の漏斗口(じょうごぐち)から引き、上豊内から中横田地域まで導く計画でしたので、下流に水が流れなくなるのではと初めは反対も多くありましたが、自ら説得に廻り文政7年(1824)ようやく着手し、3年かけて造られました。下豊内地区には2箇所、計200メートルものトンネルが掘られ当時の難工事を物語っています。嘉永年間(1848〜1853)には、用水の潤す範囲は下横田・浅井・上早川地域にも広がりました。現在も用水路は私たちの生活を支えています。
所在地 甲佐町上豊内〜上早川地域
八角塔
岩鼻神社の堂宇右側には、八角塔が建てられています。堂宇が壊れかかったので、それを修繕するため渡辺正直や渡辺持などの有志住民に呼びかけ再建にとりかかり、文政7年(1824)完成した記念の塔です。地域の加藤清正公への信仰を物語っています。
所在地 甲佐町横田(岩鼻神社内)
西住戦車長像
石碑は、甲佐町役場より北西方向約500メートル程の水田地帯の中にあります。大正3年(1914)、甲佐町仁田子に生まれた西住小次郎は、甲佐尋常小学校、旧制御船中学校を経て、陸軍士官学校に入学しました。昭和12年(1937)年支那事変が始まると戦車第一連隊の戦車長として戦線に立つことになります。昭和13年(1938)5月17日徐州会戦でクリークに遭遇して、渡河地点偵察中凶弾を受け死亡し、その際の行為が昭和の軍神として称えられました。当時は映画も製作されています。
所在地 甲佐町仁田子
カテゴリ内 他の記事
- 2024年9月18日 Created a tourism PR video for Kosa Town...
- 2025年12月16日 『甲佐町の文化財 第三集』の一般販売について
- 2025年11月27日 甲佐町の文化財探訪「糸田の大綱引き」〜令和8年1月号
- 2025年11月13日 公有化後における史跡等の管理・活用計画について
- 2025年10月28日 国指定史跡「陣ノ内城跡」の御城印の販売を開始します。