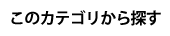後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度の対象となる人
・75歳以上の人(75歳の誕生日から自動的に加入)
・65歳から75歳未満の人で一定の障がいがある人(加入には申請が必要です。詳しくは町住民生活課へお問い合わせください)
令和6年度の保険料について
保険料の算定方法について
保険料は被保険者一人ひとりが納めます。
1人当たりの保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と個人の所得に応じる「所得割額」の合計で算出します(上限額は80万円です)。※令和6年3月31日までに75歳になった被保険者及び令和7年3月31日までに障害認定により被保険者になった方は73万円となります。
保険料は、熊本県内均一で2年ごとに見直され、医療費(自己負担分を除く)のおよそ1割になるように設定されます(およそ5割は公費(税金)、残りの4割は現役世代の保険料で賄われています)。
令和6・7年度の保険料
・均等割額 年額58,000円
・所得割額 総所得金額等(基礎控除後)×10.98% ※令和5年の総所得額等から基礎控除を差し引き、58万円未満の対象者は10.80%となります。
保険料の軽減について
所得が低い方には保険料の均等割額が軽減されます
均等割額の軽減については、世帯(被保険者全員と世帯主)の総所得金額等の合計額で計算します。
令和6年度の軽減割合については下記のとおりです。
◆保険料の均等割額の軽減(令和6年度から改正されました)
・7割軽減
43万円+{10万円×(給与・年金所得者の数-1)}以下となる世帯
・5割軽減(改正)
43万円+(29万5千円×世帯の被保険者数)+{10万円×(給与・年金所得者の数-1)}以下となる世帯
・2割軽減(改正)
43万円+(54万5千円×世帯の被保険者数)+{10万円×(給与・年金所得者の数-1)}以下となる世帯
※1「給与・年金所得者の数」とは、給与収入が55万円超の人または年金収入が125万円超の人(65歳以上の場合。65歳未満の場合は年金収入が60万円超)の合計人数です。
※2 均等割の軽減判定についての総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。また、年金所得については高齢者特別控除15万円を控除した額で判定します。
被用者保険加入者に扶養されていた方の軽減(被扶養者軽減)
制度に加入した月から2年間は均等割額が5割軽減されます。(所得割額はかかりません)
仮徴収額決定通知書の確認をお願いします
保険料を年金からの天引き(特別徴収)で納めている人は、4月から令和6年度後期高齢者医療保険料の仮徴収が始まります。
仮徴収とは、保険料額が決定する7月より前に、仮の金額として年金から徴収するものです。前回徴収した保険料額を基準として、4・6・8月の年金から徴収します。10・12・2月の徴収額との均一化を図るための仕組みです。ご理解をお願いします。
該当者には「後期高齢者医療仮徴収保険料額決定通知書」を送付します。仮徴収保険料額などが記載されていますので、ご確認ください。
あんま・はり・きゅう治療券の利用について
町では、あんま・はり・きゅうの治療を受ける場合に利用できる治療券(1人当たり1,000円の5枚)を発行しています。治療券は、町と協定を結んでいる施術院で使用できます。必要な方は、後期高齢者医療被保険者証をご準備の上、町住民生活課で申請してください。
申請期間
令和6年4月1日(月)〜令和7年3月31日(月)
医療機関の適正受診などについて
ちょっとした心掛けで適正な医療が確保されます。医療機関を受診するときは次のことに気をつけましょう。
●重複受診に注意しましょう
重複受診とは、同じ病気で同時期に複数の医療機関にかかることをいいます。受診のたびに初診料がかかり、医療費が高くなってしまいます。また、検査や処置、投薬の重複により体への負担も大きくなります。
●時間内に受診しましょう
休日や夜間などの診療時間外に受診する場合は、医療費が高く設定されています。緊急を要する重症患者への対応が遅れてしまうことにもつながります。できるだけ時間内に受診しましょう。
●かかりつけ医を持ちましょう
かかりつけ医とは、あなたの既往症や健康状態などを把握して、健康管理全般のアドバイスをする医師のことです。必要時には専門の医療機関を紹介してくれるなど、かかりつけ医を持つことは大切です。気になる症状があれば、まずはかかりつけ医師に相談しましょう。
●ジェネリック医薬品を活用しましょう
ジェネリック医薬品は新薬と同じ有効成分を使っているので、安全性も効き目も立証されています。ただし、すべての新薬に対してジェネリック医薬品があるわけではなく、症状によっては適さない場合もありますので、詳しくはかかりつけ医・薬剤師にご相談ください。
●薬のもらいすぎに注意しましょう
一度に多くの種類の薬を飲むと、薬本来の効果が出ないだけではなく、重い副作用や症状が悪化することがあります。複数の医療機関に通院中の場合は、「お薬手帳」を1冊にまとめ、受診時に必ず持参しましょう。
カテゴリ内 他の記事
- 2024年5月28日 甲佐町介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコードについて...
- 2023年9月28日 甲佐町介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコードについて...
- 2023年9月28日 甲佐町介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコードについて...
- 2024年7月2日 介護予防教室「地域の集い」について
- 2024年5月20日 後期高齢者医療制度の被保険者の皆さんへ