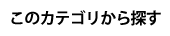甲佐町の文化財探訪 「六地蔵(ろくじぞう)が伝えるもの」〜平成29年2月号
更新日:2018年2月1日
「六地蔵(ろくじぞう)が伝えるもの」
乙女校区には六地蔵が三体残っています。
南三箇の六地蔵、下田口の六地蔵そして船津の六地蔵です。南三箇の六地蔵は熊本地震で倒れていましたが、地域の方のご尽力により、ほぼ完全な形で復元されています。
六地蔵は六体の地蔵菩薩(じぞうぼさつ)を彫り込んだ石仏で、この信仰は平安時代の終わりごろに始まったといわれており、仏教の教えの六道(地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上)の境遇(きょうぐう)にある人々の迷いや苦しみなどを救うために建てられています。供養塔(くようとう)として街道沿いに建てられることが多いようです。
南三箇の六地蔵は、享保17年(1732)に建てられ、六面に六地蔵が彫られた六地蔵塔で、他の地域の二体もほぼ同じ時期に建てられたと思われます。
この享保17年は、江戸三大飢饉(ききん)である享保の大飢饉の年で、『新甲佐町史』には、「春から翌年の春にかけて大飢饉。餓死者(がししゃ)山のごとし。糸田村も60人余餓死」「秋、蝗(いなご)が大量発生し、稲の被害甚大、飢饉で餓死者多数、翌年春の籾種(もみだね)も無く、藩より種子籾が渡される」と記されています。
大変な大飢饉(ききん)そして虫害など不安定な世から起ち直る時期にできた六地蔵であります。以来280年以上、今も地域住民の心のよりどころであり、結束の象徴でもあります。この六地蔵を見ますと、地域の人々に安らぎを与え場所として長年にわたって大切にされていることがよく伝わってきます。
文責・甲佐町文化財保護委員 赤星 眞照(有安区)
カテゴリ内 他の記事
- 2025年12月16日 『甲佐町の文化財 第三集』の一般販売について
- 2025年12月10日 緑川改修事業の促進について国土交通省に要望活動を実施
- 2025年11月27日 甲佐町の文化財探訪「糸田の大綱引き」〜令和8年1月号
- 2025年10月28日 国指定史跡「陣ノ内城跡」の御城印の販売を開始します。
- 2025年10月21日 甲佐町の文化財探訪「ラジオ放送開始100年」〜令和7年10月号...