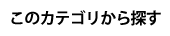甲佐町の文化財探訪 「岩下商店街の発展を見守った恵比須さん」〜平成31年3・4・5月号
「岩下商店街の発展を見守った恵比須さん」
岩下の本町通りに在る肥後銀行甲佐支店の30m程南にある三差路の一角に、商売繁盛を祈願する恵比寿神社がある。のぼり旗ひとつ無く、参拝する人も見かけない。
まず、岩下町の起源について触れたいと思う。江戸時代の記録「岩下根元記(いわしたこんげんき)」にその起源が記録されている。それによると、天正11年(1583)に現美里町の岩下集落から、伝右え門(でんうえもん)という人が移住したとある。これをきっかけに、岩下集落や西東寒野集落・上下豊内集落・上揚集落などから移住する人が続いた。
次に恵比寿神社はいつ設立されたか。「岩下根元記」によると、元和元年(1615)に小川町の仏師、柚木茂兵衛、施主 伝右え門・久五郎と記録されている。つまり、最初に移住した伝右え門が中心となり、神社を創建(そうけん)したことになる。
周囲の集落からの移住は続き、天和元年(1681)には戸数60と記録されている。商いの神を勧進(かんじん)したのは商業の街として発展しようとの目論見があったと思われる。
寛文年間(1661〜1673)に道路が整備され街並みも整えられて、岩下町と称することが許されて商業の町として発展を続けていく。初市の始まりとされる9(く)の市が始まっている。
正徳5年(1715)に渡辺酒造が、天保14年(1843)に甲斐酒造が起業されて、商業の町に加え、製造業も盛んになってきている。
明治11年(1878)は西南戦争が終わった直後であるが、岩下町の人口や職業別の統計があるので、それを掲げる。
この統計データで読み取れるのは人口の増加と共に、色々な職種の仕事が展開されてきたこと、旅籠屋(はたごや)が14軒と多いのに驚く。
| 戸数 | 人口 | 人力車 | 荷車 | 馬 | 造酒職 | 質屋 | 染物職 | 水車職 | 鍛冶職 |
| 166戸 | 786人 | 3輌 | 8輌 | 1頭 | 2軒 | 3軒 | 1軒 | 1軒 | 5軒 |
| 紙漉職 | 絞油職 | 旅籠屋 | 穀物屋 | 造酢職 | 農業 | ||||
| 1軒 | 1軒 | 14軒 | 1軒 | 1軒 | 0軒 |
昭和の時代に入り、岩下町を核にして道路や鉄道が延伸されると、砥用町や中央町の人々の往来が盛んになり、商店街は一層発展をつづけた。その姿を恵比寿さんは見守っていたように思う。恵比寿さんの祭日は11月20日、甲佐神社の神主を招いて祝詞(のりと)をあげ、参拝した。
昭和32年(1957)の商業統計が商工会の調査書に記載があるので、どこまで岩下町が発展をしたかをしめしておく。この資料は岩下と緑町の職業別の統計である。商店数は111軒に及んでいる。名店会も春の市・中元大売出し・恵比寿市大売出し・年末大売出しと季節ごとに市を開いて繁栄を試みてきた。
しかし、この頃を境にして商店街は膵尾(すいび)の一途をたどることになる。
| 衣料 | 畳 | 自転車 | 文具 | 食料 | 薬店 | 肥料雑穀 | 鮮魚 | 酒屋 | 履物 |
| 2 | 2 | 5 | 5 | 21 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 |
| 運動具 | 小間物 | 薪炭 | 金物 | 飲食店 | クリーニング | 菓子 | 農機具 | 肉屋 | その他 |
| 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 19 |
総計111
文責・甲佐町文化財保護委員 清村 一男(下豊内区)
カテゴリ内 他の記事
- 2024年9月18日 Created a tourism PR video for Kosa Town...
- 2025年12月16日 『甲佐町の文化財 第三集』の一般販売について
- 2025年11月27日 甲佐町の文化財探訪「糸田の大綱引き」〜令和8年1月号
- 2025年11月13日 公有化後における史跡等の管理・活用計画について
- 2025年10月28日 国指定史跡「陣ノ内城跡」の御城印の販売を開始します。