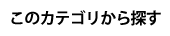甲佐町の文化財探訪「田原区「十一面観音」の移転」〜令和5年1月号
「田原区「十一面観音」の移転」
令和四年九月八日に田原区の『十一面観音像』の移転式が行われました。
移転の理由は、田原区内を通る県道今吉野甲佐線の拡幅工事計画によるもので、移転先は30m程南の町所有地(消防車車庫、消火栓設置場所)となります。
移転式典に当たって、御船町の「大師寺(タイシジ)」より僧侶を招き、観音堂の解体に伴う遷座(センザ)法要と、新観音堂落慶(ラッケイ)に伴う入仏法要が営まれました。移転式には区民の方20名程が参加されておりました。
新しいお堂は高さ3.3m、間口1.8m、奥行き2.0mの木造切妻反り屋根造りとなっております。観音像は高さ約74cm石造り立像で、背面には『嘉永六年丑年二月』と刻まれており、江戸時代末期の一八五三年に造られたものであることがわかりました。
この辺りは古い時代から拓けていたようで、麻生原区や隣接する府領区と同様に、石器や土器も多く出土しております。また、千五百年代は群雄割拠の戦国時代で、当時の肥後・熊本は豊後の大友氏、肥前の龍造寺氏、薩摩の島津氏による争奪戦場となっていたようです。併せて熊本の豪族阿蘇氏の南北分裂に伴う激しい戦いの場でもあったようです。
同区グリーンセンター入口には大永五年(1525)に先人達が生前仏事を営んで自分の後生安泰を願って、逆修碑(ぎゃくしゅうひ)が建立されており、当時から信仰心も強かったのではないでしょうか?
皆さん方の話では、十一面観音に伴う祭事として以前は一月十七日と七月十七日に行われていたが、現在は一月十七日のみ各家庭で作った料理を持ち寄って、お祭りと懇親会を行っておられるようです。
十一面観音像は地域を守る守護神として人々から崇拝され、大切にされている様子が伺えました。
文責・甲佐町教育委員会 北里 義友(津志田区)
カテゴリ内 他の記事
- 2024年9月18日 Created a tourism PR video for Kosa Town...
- 2025年12月16日 『甲佐町の文化財 第三集』の一般販売について
- 2025年11月27日 甲佐町の文化財探訪「糸田の大綱引き」〜令和8年1月号
- 2025年11月13日 公有化後における史跡等の管理・活用計画について
- 2025年10月28日 国指定史跡「陣ノ内城跡」の御城印の販売を開始します。