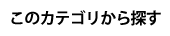町総合保健福祉センター「あゆみだより」〜高齢者の権利を守る制度や事業〜
高齢者を守るための制度や事業についてご存知ですか?
高齢者を守るための制度〜成年後見制度〜
成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で、判断能力の不十分な方は不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分にこれらのことを行うのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても、判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々に対し、本人の権利を守る援助者(後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度には大きく2つの種類があります。
任意後見制度
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について、代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおく制度です。
法定後見制度
法定後見制度は、判断能力が不十分になってから、本人・配偶者・4親等内の親族・検察官・町長などが家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が法定後見人および法定後見監督人を選任し、本人の財産管理などの法律行為を支援する制度です。法定後見制度は、本人の判断能力の状態等に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの種類に分かれます
- 「後見」 … 「判断能力が欠けているのが通常の状態の方」が対象となり、支援を行う「後見人」に対し、日常生活に関する行為以外の行為に対する取消権、財産に関するすべての法律行為に対する代理権が与えられます。
- 「保佐」 … 「判断能力が著しく不十分な方」が対象となり、支援を行う「保佐人」に対し、借金・訴訟問題・相続の承認や放棄・新築や増改築などについての代理権(民法13条1項に定める行為)や、本人が選択した内容について、不利益が生じると判断されることに対しての取消権(申立ての範囲内で、家庭裁判所が定める特定の法律行為)が与えられます。
- 「補助」 … 「判断能力が不十分な方」が対象となり、支援を行う「補助人」に対し、借金・訴訟問題・相続の承認や放棄・新築や増改築などについて、本人の同意を得た代理権(民法13条1項に定める行為の一部)や、本人が選択した内容について、不利益が生じると判断されることに対しての取消権(申立ての範囲内で、家庭裁判所が定める特定の法律行為)が与えられます。
成年後見制度の最大の目的は、支援が必要な高齢者等(成年被後見人等)の財産を保全・維持することが最優先となるため、成年後見人が選任されている方の財産処分等を行うためには、家庭裁判所の事前許可が必要になり、不必要な財産処分を防ぐことができます。
法定後見人の申立てに関しては、原則的には家族などの4親等内親族が行いますが、身寄りがない方などに対しては、町長が本人に代わって申立てを行うことが可能です。認知症などにより判断能力が低下する前に、後見人などを準備しておくことは重要ですが、判断能力が不十分となってしまった身寄りのない方でも、成年後見制度の利用が可能です。
成年後見制度に関してのご相談は、町福祉課(234-1114)へご相談ください。
高齢者を守るための事業〜地域福祉権利擁護事業〜
熊本県社会福祉協議会から甲佐町社会福祉協議会が事業委託を受けて実施する事業で、ご自分で金銭や大切な書類を管理することに不安のある方の財産や権利を守るため、日常的な金銭管理や通帳・権利証等、大切な書類を預かることを通して、利用者が安心して地域で生活を送れるように支援をする事業です。
ご利用できる方
町内で在宅生活をされている認知症、知的障がい、精神障がい等により、判断能力に不安のある方で、事業についての理解ができ、契約できる能力を有する方
契約の締結
利用者本人と町社会福祉協議会で契約締結後、サービス開始となります。
サービスの内容
- 福祉・介護サービスの利用する際の手続きに対する援助サービス
- 年金や福祉手当等の受領に必要な手続きや、医療費・税金・公共料金等の支払いに対する手続き及び支払いに伴う預貯金の払い出し、または預け入れ等の日常的金銭管理サービス
- 年金証書や預貯金の通帳、権利書や契約書類、実印、銀行印などの大切な書類等の預かりサービス
地域福祉権利擁護事業に関してのご相談は、甲佐町社会福祉協議会(234-1192)へご相談ください。
自分自身や家族の将来を見据えて
今後、団塊の世代が後期高齢者に到達する令和7年(2025年)までは、県や国の全体で高齢化率の上昇が予想されています。町においても、独居高齢者や高齢者のみ世帯の増加が見込まれており、自分や家族の将来を見据えた準備を行っていく必要があります。
まずは、認知症を予防するような文化的・社会的な活動を送ることが大切ですが、認知症が疑われる状態になった際には早期の相談・受診ができるように情報を収集しておくことも重要です。町では、住民向けに認知症に関する講演会や、相談会を開催していますので、ぜひご活用ください。
カテゴリ内 他の記事
- 2023年8月31日 心配ごとにかかる各種相談会と在宅高齢者緊急通報システムについ...
- 2025年12月17日 寒さに負けないからだでフレイル・転倒を予防しよう〜総合保健福...
- 2025年11月7日 冬の血圧に気をつけましょう〜総合保健福祉センター「健康だより...
- 2025年9月10日 骨粗鬆症について〜総合保健福祉センター「健康だより」(2025年1...
- 2025年8月8日 いつ、どう食べるか、を意識してみましょう 〜 総合保健福祉セ...