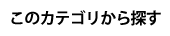生活習慣病があると骨が弱くなる?〜総合保健福祉センター「健康だより」(2023年6月)
生活習慣病から骨粗しょう症を起こすと連想する人は少ないと思いますが、実は両者には深い関わりがあります。生活習慣病があると骨密度が減少するだけでなく骨質が悪くなるので、病気のない人に比べて骨折リスクが高くなることが分かっています。どちらも自覚症状が現れにくいため、重症化してはじめて病気の存在に気づくことが少なくありません。
骨粗しょう症と関連が深い生活習慣病とは
骨粗しょう症による骨折のリスクが高いことがわかっている生活習慣病は、2型糖尿病、慢性腎臓病(CKD)、慢性閉塞性肺疾患(COPD)です。これらの生活習慣病では、骨質を悪くさせる重要な病態として関与しています。
本町の骨折患者の多くに糖尿病や腎臓病の既往歴がありました。
糖尿病が骨を弱くする理由とは
糖尿病は骨の健康にどのように影響するのでしょうか。これには、インスリンというホルモンが関係します。食事から摂った炭水化物は、糖質に分解されてブドウ糖となり、肝臓へ蓄えられて必要な分だけ血液中に送られ、筋肉などに取り込まれてエネルギー源として使われます。このブドウ糖の量を一定範囲内に調節しているのがインスリンです。インスリンの働きが悪くなる、分泌量が低下すると、ブドウ糖が血液中に過剰に増え血糖値が上がった状態が続くのが糖尿病です。
また、インスリンは骨をつくる骨芽細胞を増やす作用もあるため、糖尿病でインスリンの作用が低下すると、骨の新陳代謝で「つくる」よりも「壊す」働きの方が強くなり骨密度が低下します。
その他、インスリンには腎臓でビタミンDを活性型ビタミンDにする働きがあり、活性型ビタミンDは腸管におけるカルシウムの吸収に欠かせません。糖尿病でインスリンの作用の低下や分泌量の不足があると、食事でカルシウムを摂っても吸収されにくく、さらには、血糖値が高い状態が続き、尿の量が増えるとカルシウムが体から出ていき、体内のカルシウム不足を骨のカルシウムで補うため、ますます骨密度が減少します。糖尿病は骨密度の他、骨に含まれるコラーゲンの劣化を引き起こします。コラーゲンが劣化すると骨質が低下し、骨のしなやかさや強度が失われ、骨折しやすくなります。
朝食を取ると胃や腸などの消化器官にスイッチが入り、体温が上がります。ご飯やパンなどの糖質は体を動かすエネルギーになり、肉・魚・卵・大豆製品・乳製品などのタンパク質は体をつくる源となります。
糖尿病による骨折のリスクを減らすためには
健康診査を受けで血糖値の状況を確認し、生活習慣を見直す。治療中の場合、血糖のコントロールを良好に保ち治療を継続することです。症状がないからと放置すると全身にさまざまな障害を起こし骨折のリスクも高めます。早期発見、早期治療とともに、骨の健康対策も心がけることが大切です。
カテゴリ内 他の記事
- 2023年8月31日 心配ごとにかかる各種相談会と在宅高齢者緊急通報システムについ...
- 2024年3月12日 日々の運動習慣を応援するアプリを紹介します〜総合保健福祉セン...
- 2024年1月30日 高齢者の肥満は要注意!「サルコペニア肥満」とは〜総合保健福祉...
- 2023年11月27日 歯科検診を受けましょう〜総合保健福祉センター「健康だより」(2...
- 2023年10月11日 糖尿病の話〜総合保健福祉センター「健康だより」(2023年11月)...