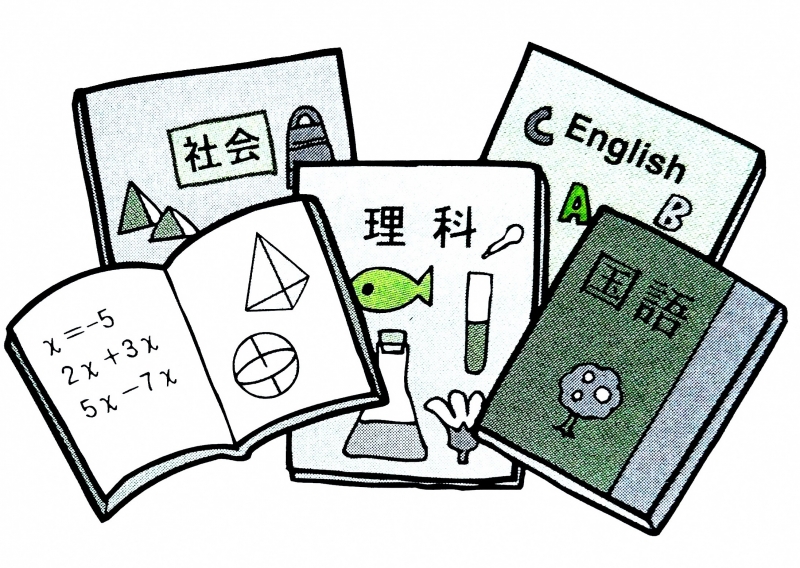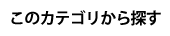自分に関わりのあることとして同和問題を考える
更新日:2019年2月15日
芸能や文化との関わり
中世(鎌倉・室町時代)には、千秋万歳、曲舞や猿楽などと呼ばれる、歌や踊りなどの遊芸、芸能などが発達しました。また、庭園づくりなど、現在につながる様々な文化も発達しました。これらを支えたのは農業以外で生活をしていた人たちで、封建社会体制の支配に属さないため差別されていました。
しかし、この人たちの中には、農民の間に生まれた田楽や猿楽を世界最古の舞台芸能である能楽として大成した観阿弥・世阿弥父子、また庭師として銀閣や相国寺、興福寺等の庭を手がけたとされる善阿弥父子等、現在まで残る文化を形成した人たちが数多くいます。このように、当時差別された人たちが、今日の伝統芸能や文化に果たした功績は大きいものがあるのです。
義務教育教科書無償運動
昭和30年代後半、憲法の「義務教育は無償である」ということについての学習を深めた、高知県の同和地区の人たちを中心に、教科書無償の運動が起こりました。〜中略〜この運動は生活の安定と向上、部落差別の解消につながる取組みでもありました。やがて、この運動は全国へ広がり、ついに国会でも取り上げられました。
そして、昭和38(1963)年に「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」が制定されたのです。現在は、教科書が無償で配付されることが当然のようになっていますが、ここに至るまでには、このように多くの人たちの取り組みがかかわっているのです。
人権研修テキスト(同和問題編)より
カテゴリ内 他の記事
- 2026年2月6日 みんなの人権セミナーinくまもと開催

- 2025年12月10日 令和7年度甲佐町学校人権教育部会授業研究会を開催
- 2025年5月21日 人権に関するDVDのご紹介
- 2025年3月18日 ジェンダー平等を考えよう
- 2023年11月2日 第51回熊本県人権教育研究大会