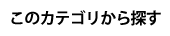甲佐町の文化財探訪「明治45年(1912)7月13日の大洪水」〜令和2年8月号
「大正元年(1912)7月13日の大洪水」
明治45年(1912)7月13日の大洪水は、寛政8年(1796)辰(たつ)の年の大洪水以上の水かさで、鵜ノ瀬堰はもちろん上揚、上豊内、仁田子、大町その他の堤防も各所が決壊して、宮内、甲佐、白旗の人家の流失、水田の荒廃等を極めました。今から108年前のことです。この明治45年の緑川大洪水については、下横田消防倉庫の横にある明治45年(1912)建立の猿田彦大明神(さるたひこだいみょうじん)の台座に記録が残っています。碑文(ひぶん)は歳月による風化で判読困難な部分も多いのですが「驟雨(しゅうう)的豪雨」によって、「明治45年7月13日弐十時増水」「宮内豊内仁田子有安下横田塔木糸田所属堤防拾余箇所潰」に至ったことが読み取れます。
この碑文の近くの小鶴に御崎(みさき)大明神があります。お堂はとても立派であり、地域の人々が大事にしている様子がうかがえます。奥の厨子(ずし)には石造(凝灰岩製)神像2体が安置されています。横の古びた小さな厨子には損傷の激しい神像が3体安置されています。厨子内のそれぞれの神像の由来を記すものはありません。
古老の話では、
「明治45年囲緑川大洪水が起こり鵜ノ瀬堰をはじめ各所堤防が決壊し、人家の流出、水田は根こそぎ流される惨状となる記録的な大災害であった。仁田子堤防の決壊に伴い水崎大明神は下横田小鶴に茶畑に漂流した。翌年下横田の人々は御崎大明神と改め木造藁ぶきの堂を建てた」と伝えられているそうです。
また九折(つづら)に六地蔵石幢(せきどう)が建っています。地上高2m、六角周り96cmの大きさです。全面がすっかり摩耗しており、地蔵尊の輪郭さえもわかりません。この六地蔵も明治45年の大洪水で現在地に流れ着いたと伝えられています。
これら先人の残した遺跡から私たちが学ばねばならないことは数多くあります。自然災害の惨状を想定外の言葉で表現することがありますが、先人の残した記録を読めば、なすべきことは自ずと出てくるように思えます。


下横田消防倉庫横の猿田彦大明神
 小鶴の御崎大明神
小鶴の御崎大明神  ※九折の六地蔵幢は民有地に所在するため、場所については伏せさせていただきます。 文責・甲佐町文化財保護委員 赤星 眞照 (有安区)
※九折の六地蔵幢は民有地に所在するため、場所については伏せさせていただきます。 文責・甲佐町文化財保護委員 赤星 眞照 (有安区)
カテゴリ内 他の記事
- 2025年12月16日 『甲佐町の文化財 第三集』の一般販売について
- 2025年12月10日 緑川改修事業の促進について国土交通省に要望活動を実施
- 2025年11月27日 甲佐町の文化財探訪「糸田の大綱引き」〜令和8年1月号
- 2025年10月28日 国指定史跡「陣ノ内城跡」の御城印の販売を開始します。
- 2025年10月21日 甲佐町の文化財探訪「ラジオ放送開始100年」〜令和7年10月号...