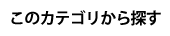甲佐町人権尊重のまちづくり条例を制定しました
甲佐町では、全ての人が不当な差別を受けることなく、個人として尊重され、生き生きと暮らすことができる人権尊重のまちづくりを推進していくため、「甲佐町人権尊重のまちづくり条例」を令和4年3月に制定しました。
甲佐町人権尊重のまちづくり条例(解説入り)
(前文)
全ての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。これは、世界人権宣言にうたわれている人類普遍の原理であり、基本的人権を侵すことのできない永久の権利として全ての国民に保障している日本国憲法の精神にかなうものである。
甲佐町は、日本国憲法その他の法令等を遵守し、これまで、甲佐町人権の町づくりに関する条例(平成7年条例第21号)、甲佐町人権教育・啓発基本計画(平成23年12月策定)等に基づき、互いの理解と協力と信頼により、人権が尊重された明るく住みよいまちを築くことをめざし、人権・同和教育と啓発に関する様々な施策を推進してきた。
しかしながら世の中には、依然として、社会的身分、門地、人種、信条、性別、障がい、疾病等による不当な差別の発生等の人権侵害が存在しており、また、国際化、情報化等の進展など社会情勢の変化に伴い、様々な人権課題も生じている。
このような状況を踏まえ、町、町民及び事業者等が協力して、不当な差別の解消と人権課題の解決に向けて、人権尊重の理念の普及をより一層推進していく必要がある。
また、一人ひとりが、様々な人権問題について正しく理解し、差別を許さないという意思を態度や行動に表していかなければならない。
ここに、全ての町民が不当な差別を受けることなく、個人として尊重され、生き生きと暮らすことができる人権尊重のまちづくりを推進していくため、この条例を制定する。
【前文の解説】
国連主導の世界人権宣言や日本国憲法第11条の基本的人権の享有を基に、甲佐町では平成7年に「甲佐町人権の町づくりに関する条例」を施行しました。
この条例に基づき、人権問題についての正しい理解と認識を深め、差別のない明るい社会をめざした教育・啓発活動を推進するとともに、平成23年12月にはあらゆる差別をなくすため「甲佐町人権教育・啓発基本計画」を策定し、町民一人ひとりが正しく人権を理解し、行動できるよう取り組んでいます。
しかしながら、今もなお同和問題をはじめとし、子ども、高齢者、障がい者、女性、外国人、アイヌの人々、エイズ患者、HIV感染者、ハンセン病回復者、刑を終えて出所した人、犯罪被害者等に対するインターネットや電子メールを悪用した人権侵害などが後を絶ちません。とりわけ、子どものいじめや自殺、不登校、家庭内での子どもへの暴力、育児放棄、高齢者に対する偏見や虐待などは、大きな社会問題となっています。また、少子化と平均寿命の延びなどにより、高齢化社会を迎えるなど、人権問題をめぐる状況は複雑化、多様化の傾向にあります。これらの社会変化を背景にして、国では「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(平成28年法律第68号)及び「部落差別の解消の推進に関する法律」(平成28年法律第109号)と相次いで人権に関する法律を制定しました。
甲佐町でも、これらの法令の趣旨にのっとり、あらゆる差別をなくすために、人権尊重の実現は、私たち一人ひとりの課題であることを再認識し、これからも全ての人の人権が尊重されるまちづくりに取り組んでいくことを決意し、本条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、前文に示す趣旨のもと、人権尊重のまちづくりに関し、町、町民、事業者等の責務と役割を明らかにするとともに、人権に関する施策の基本となる事項を定めることにより、人権尊重のまちづくりを総合的かつ計画的に推進し、もって人権を尊重し、共に生きる社会の実現に資することを目的とする。
【第1条の解説】
この条例の目的は、人権が尊重されるまちづくりの実現にあります。そのためには本町に暮らす全ての人(住民票の有無などを問わず)、事業者等が連携・協働して人権に関する施策を推進し、全ての差別のない社会づくりを目指します。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)町民 町内に居住し、勤務し、在学し、又は滞在する者をいう。
(2)事業者等 町内に事務所又は事業所を有し、事業を営む法人その他の団体又は個人をいう。
【第2条の解説】
(1) 町民
本条例においては、町内在住者に限らず在勤、在学者のほか、何らかの目的をもって町内を訪れ、期間を問わず滞在する者を町民と定義しています。
特に「滞在する者」については、観光や通勤、買い物等、何らかの目的をもって一時的に町内に滞在する者を含めるものとします。
(2) 事業者等
事業者等は、町内で事業を営む事業所、事務所、営業所、店舗等を有する法人、その他の各種団体及び個人事業主などをいいます。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、周知・啓発を図り、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政の全ての分野で町民及び事業者等の人権意識の高揚に努めるものとする。
【第3条の解説】
第1条に定める目的を達成するため、行政として周知・啓発を図り、必要な施策を積極的に推進し人権尊重のまちづくりをすすめていきます。そして、町と町民、事業者等が一体となって取り組みを推進するため、これらの活動への参加を保障し、人権意識の高揚を図ることを町の責務としています。
(町民の役割)
第4条 町民は、相互の基本的人権を尊重し、自らが人権のまちづくりの担い手であるということを認識して、学校、家庭、職場、地域その他のあらゆる生活の場において、人権意識の高揚に努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する差別をなくすための人権施策に協力するよう努めるものとする。
【第4条の解説】
全ての町民に、等しく人権が尊重されることはもちろん、自らの権利だけではなく他者の人権を尊重し、差別を許さないという自覚をもち、国、県、町等が実施する人権尊重のまちづくりに対しての町民の役割を求めるものとします。
(事業者等の役割)
第5条 事業者等は、基本的人権を尊重し、事業活動に関わる者の人権意識の高揚を図るとともに、町が実施する人権施策に協力するよう努めるものとする。
【第5条の解説】
事業者等は、自らの経済的活動のなかに人権の視点の必要性を再認識して、事業活動が地域に影響を及ぼすことに配慮し、人権意識の向上と人権が尊重されるまちづくりの実現を図るため、あらゆる差別の解消、就職の機会均等と社会参加が保障される体制づくり等に積極的に努めていただくものとします。
(施策の推進)
第6条 町は、あらゆる不当な差別をなくすため、教育及び社会福祉の充実並びに人権擁護の施策を総合的に推進するものとする。
【第6条の解説】
町は、全ての差別の撤廃に向けて人権教育・啓発に取り組み、差別のない安全で安心なまちづくりを進めていきます。
(調査等の実施)
第7条 町は、不当な差別の解消と人権課題の解決に向けて、国、県が実施する人権に関する調査に、各種関係団体と連携を図り、協力するものとする。
【第7条の解説】
国、県が実施する人権に関する調査に、各種関係団体と連携を図り協力をすることにより、必要に応じて実態の把握に努めます。
(相談体制の整備)
第8条 町は、国及び県との適切な役割分担を踏まえ、人権に対する相談に的確に応じるための相談体制の整備に努めるものとする。
【第8条の解説】
人権を侵害する行為は多様化しており、様々な立場の町民がいる中で、誰もが安心して気軽に相談できるための体制の整備に努めます。
(人権教育及び啓発活動の推進)
第9条 町は、町民、事業者等の人権意識の普及高揚を図るため、人権に関する教育及び啓発活動の推進を図り、人権尊重の社会づくりに努めるものとする。
【第9条の解説】
人権問題は、偏見や誤解、理解不足や無関心など、人権意識の欠如が原因となっている場合が多くあるため、町民、事業者等が人権に対する理解を深め、人権の尊重に対する意識を高めることを目的に、町が啓発及び教育の推進を図ります。
(推進体制の充実)
第10条 町は、前条の施策を推進するため、国、県及び各種関係団体との連携を強化し、人権施策の推進体制の充実に努めるものとする。
【第10条の解説】
人権が尊重されたまちづくりの実現を図るためには、国、県、関係団体等との連携が不可欠です。また、学校や行政といった公的機関以外にも事業所等をはじめ、人権確立のために活動している団体等との連携を深め、推進体制の充実を図ります。
(審議会)
第11条 町は、人権擁護に関する重要事項を調査審議するため、甲佐町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。
【第11条の解説】
甲佐町人権擁護審議会は、地方自治法138条の4第3項の規定に基づく執行機関の付属機関で審議等を行う位置づけにあり、人権が尊重されるまちづくりを推進していくにあたり、必要な事項を審議することとします。
(雑則)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
【第12条の解説】
条例に関し必要な事項は別に定めるものとします。
カテゴリ内 他の記事
- 2025年12月12日 甲佐町人権教育講演会(ミニコンサートあり)を開催します
- 2025年12月10日 令和7年度甲佐町学校人権教育部会授業研究会を開催
- 2025年8月28日 町生涯学習センター・図書室「人権コーナー」の紹介
- 2025年7月14日 甲佐町人権教育推進協議会総会が開催されました
- 2025年5月21日 人権に関するDVDのご紹介