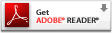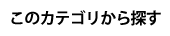高齢者などの権利を守る制度と相談会について〜地域包括支援センター「健康だより」(令和7年8月)
高齢者などを守るための制度〜成年後見制度〜
高齢者などの権利を守るための制度や事業についてご存じですか。認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な人は、自身の不動産や預貯金などの財産管理、介護保険や障がい福祉サービスの利用や施設入所に伴う契約締結、遺産分割協議などの行為が必要であっても、自身でこれらのことを行うのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても適切な判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法などの被害に遭う恐れもあります。
成年後見制度とは、このような判断能力が不十分な皆さんに対し、本人の権利を守る援助者(後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度には大きく2つの種類があります。
任意後見制度
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来に判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活・療養看護や財産管理に関する事務について、代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおく制度です。
法定後見制度
法定後見制度は、判断能力が不十分になってから、本人・配偶者・4親等内の親族・検察官・町長などが家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が法定後見人および法定後見監督人を選任し、本人の財産管理などの法律行為を支援する制度です。法定後見制度は、本人の判断能力の状態に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの種類に分かれます。
成年後見制度の最大の目的は、支援が必要な高齢者等(成年被後見人等)の財産を保全・維持することが最優先となるため、成年後見人が選任されている人の財産処分などを行うためには、家庭裁判所の事前許可が必要になり、不必要な財産処分を防ぐことができます。
法定後見人の申立てに関しては、原則的には家族などの4親等内親族が行いますが、身寄りのない人などに対しては、町長が本人に代わって申立てを行うことが可能です。認知症などにより判断能力が低下する前に後見人などを準備しておくことは重要ですが、判断能力が不十分となってしまった身寄りのない人でも、成年後見制度の利用が可能です。
成年後見制度に関してのご相談は、町福祉課地域包括支援係(甲佐町地域包括支援センター)(234-1114)へご相談ください。
高齢者を守るための事業〜地域福祉権利擁護事業〜
熊本県社会福祉協議会から甲佐町社会福祉協議会が事業委託を受けて実施する事業で、ご自分で金銭や大切な書類を管理することに不安のある人の財産や権利を守るため、日常的な金銭管理や通帳・権利証などの大切な書類を預かることを通して、利用者が安心して地域で生活を送れるように支援をする事業です。
ご利用できる方
町内で在宅生活をされている認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力に不安のある人で、事業についての理解ができ、契約できる能力を有する人
契約の締結
利用者本人と県社会福祉協議会で契約締結後、サービス開始となります。
サービスの内容
1.福祉・介護サービスを利用する際の手続きに対する援助サービス
2.年金や福祉手当などの受領に必要な手続きや、医療費・税金・公共料金などの支払いに対する手続きおよび支払いに伴う預貯金の払い出し、または預け入れなどの日常的金銭管理サービス
3.年金証書や預貯金の通帳、権利証や契約書類、実印、銀行印などの大切な書類の預かりサービス
地域福祉権利擁護事業に関してのご相談は、町社会福祉協議会(234-1192)へご相談ください。
暮らしに関する相談会について
高齢者・障がい者のための弁護士電話法律相談(問い合わせ先:熊本県弁護士会 TEL:325-0913)
県弁護士会では、毎週月・木曜日の午後1時から4時(祝祭日以外)に電話法律相談を実施しています。高齢者や障がい者問題に取り組む弁護士が、ご本人、ご家族、支援者の皆さんのさまざまな悩みに応じます。
毎週 月曜日と木曜日(午後1時から午後4時まで)
無料弁護士電話法律相談 TEL:0120-57-9960
詳細は「高齢者・障がい者のための弁護士電話法律相談」をご確認ください。
高齢者・障がい者のためのなんでも相談箱(問い合わせ先:熊本県弁護士会 TEL:325-0913)
県弁護士会では、高齢者・障がい者の方に関する相続、離婚、交通事故、成年後見などに関するさまざま心配ごとに対して、相談対応を行っています。ご本人だけでなく、ご家族や援護者、行政機関、福祉団体、病院、施設等からの相談にも対応可能です。
相談申し込み方法 相談申込書に必要事項を記載し県弁護士会へFAX(096-325-0914)
相談対応 相談申込後に県弁護士会の電話相談担当の弁護士から折り返し電話
詳細は「高齢者・障がい者のためのなんでも相談箱」をご確認ください。
司法書士による成年後見無料相談(問い合わせ先:熊本県司法書士会 TEL:364-2889)
県司法書士会が月に2回、無料で開催する相談会で、成年後見制度に関する相談に応じます。熊本県司法書士会館での面接相談と電話での相談が可能です。
毎月 第2水曜日と第4水曜日(午後5時30分から午後7時30分まで)
相談専用電話番号 096-361-2944
相談会場 熊本県司法書士会館2階相談室(熊本市中央区大江4丁目4番34号)
詳細は「司法書士による成年後見無料相談」をご確認ください。
法律・人権・行政相談(問い合わせ先:町地域包括支援センター TEL:234-1114)
町が実施する相談会で、相談員として委嘱した弁護士、行政相談委員、人権擁護委員、民生・児童委員が対応し、原則、毎月第1月曜日の午前9時から正午まで、甲佐町町民センターで開催しています。
心配ごと相談(問い合わせ先:町地域包括支援センター TEL:234-1114)
町が実施する相談会で、相談員として委嘱した民生・児童委員が対応し、原則、毎月第3月曜日の午前9時から正午まで、甲佐町町民センターで開催しています。
消費生活相談室(問い合わせ先:町福祉課 福祉係 TEL:234-1114)
生活上の消費問題(インターネットトラブル、さまざまな商法トラブル)やカードローン、消費者金融などの相談に、専門の相談員が対応します。相談は、毎週木曜日の午前9時から正午までと、午後1時から午後4時まで、甲佐町老人いこいの家で開催しています。(相談日には、直接電話での相談が可能です。連絡先:234-3223)
悩みはまず、相談しましょう
生活上の悩みごとや、介護保険サービスの利用方法など、どうしたらよいか分からないことがあれば、まずはご相談ください。
追加情報
この記事には外部リンクが含まれています。
カテゴリ内 他の記事
- 2025年11月19日 甲佐町おやこ手帳(電子母子健康手帳アプリ)を導入しました
- 2025年10月20日 令和7年度甲佐町新婚生活応援事業
- 2025年9月12日 被災者生活再建支援制度のご案内
- 2025年9月10日 不足額給付金の提出期限は10月31日(金)です
- 2025年8月18日 災害に便乗した悪質商法にご注意ください