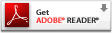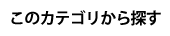医療費が高額になった場合は高額療養費制度を活用しましょう
国民健康保険の高額療養費制度について
国民健康保険被保険者が高額な医療費を支払ったときは、「高額療養費制度」で払い戻しを受けられる場合があります。
高額療養費制度とは
高額療養費制度とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、後から払い戻される制度です。
※入院時の差額ベッド代や食事代、保険外診療は対象外です。
高額療養費の申請に必要なもの
- 国民健康保険高額療養費支給申請書 支給申請書(PDF 約55KB)
(支給対象者には町から申請書が送付されます。) - 医療機関などで発行された医療費の領収証または支払証明書など
- 世帯主名義の預金口座番号などが分かるもの
- 世帯主のマイナンバー(個人番号)が分かるもの
申請およびお問い合わせ先
町住民生活課保険係
自己負担限度額とは
自己負担限度額は、同じ世帯内の国保被保険者や世帯主の年齢および所得状況などにより下記のとおり設定されています。
70歳未満の人の自己負担限度額
同じ被保険者が同じ月内に同じ医療機関に支払った一部負担金が、下表の限度額を超えたときは、超えた分が支給されます。
| 所得区分 | 基準総所得額 | 年3回目まで | 年4回目以降 |
|---|---|---|---|
| ア | 901万円超 | 252,600円 (総医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) | 140,100円 |
| イ | 600万円超〜901万円以下 | 167,400円 (総医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) | 93,000円 |
| ウ | 210万円超〜600万円以下 | 80,100円 (総医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) | 44,400円 |
| エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
| オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※基準総所得額とは、前年の総所得金額などから基礎控除33万円を引いたものです。
※住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人です。
※過去12カ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額は下がります(表中「年4回目以降」の金額)。
※同じ世帯で1カ月に各医療機関に21,000円以上支払った場合が2回以上あり、それらの合計額が自己負担限度額を超えたとき、超えた分を支給します。
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額
外来(個人単位)の限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 年4回目以降 |
|---|---|---|---|
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) | 252,600円 (総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分 の1%を加算) | 140,100円 | |
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) | 167,400円 (総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分 の1%を加算) | 93,000円 | |
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) | 80,100円 (総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分 の1%を加算) | 44,400円 | |
| 一般 | 18,000円 (年間上限※144,000円) | 57,600円 | 44,400円 |
| 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | ‐ |
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 | ‐ |
- 「現役並み所得者」とは、同一世帯内に住民税課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
- 「一般」とは、現役並み所得者および低所得者2・1以外の人
- 「低所得者2」とは、70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)
- 「低所得者1」とは、70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の場合は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
※「年間上限」は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
高額療養費外来年間合算について
平成29年8月に高額療養費制度について見直しが行われ、年間を通じて高額な外来診療を受けている70歳以上の人の負担が増えないように、自己負担額の年間上限の制度(外来年間合算)が設けられました。
基準日(7月31日)時点で所得区分が一般または低所得者1・2の70歳〜74歳の被保険者について、計算期間(通常8月1日から翌年7月31日)内に外来診療で負担した医療費が14万4,000円を超えた場合に、その超えた分が支給されます。対象となる方には、支給申請の案内を送付してお知らせします。ただし、計算期間中に被用者保険(社会保険等)から甲佐町国民健康保険に加入した場合は、自己負担額の総額が把握できないため、該当になる場合でも支給申請の案内が送られないことがあります。
また、被用者保険(社会保険等)に申請する際の自己負担額証明書(計算期間中の自己負担額が記載されているもの)が必要な場合は窓口までご相談ください。
高額介護合算療養費について
高額介護合算療養費制度は、同じ世帯の被保険者が1年間に支払った医療保険と介護保険における自己負担額を合算し、限度額を超えた場合にその超えた分を支給する制度です。
対象となる方には、支給申請の案内を送付してお知らせします。この制度は、通常8月1日から翌年7月31日までを1年間として計算されます。この期間に被用者保険(社会保険等)から甲佐町国民健康保険に加入した場合は、自己負担額の総額が把握できないため、該当になる場合でも支給申請の案内が送られないことがあります。
また被用者保険(社会保険等)に申請する際の自己負担額証明書(計算期間中の自己負担額が記載されているもの)が必要な場合は窓口までご相談ください。
医療費が高額になりそうなときには「限度額適用認定証」を利用しましょう
医療費が高額になることが事前に分かっている場合には、申請により町が発行する「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。
※マイナ保険証を利用すれば、事前に「認定証」の交付を受けなくても、医療機関などの窓口での支払いが限度額までになります。更新手続きも不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。追加情報
カテゴリ内 他の記事
- 2025年11月19日 マイナンバーカードと健康保険証の一体化はお済みですか?
- 2026年1月5日 産前産後期間の国民健康保険税が免除されます

- 2025年12月12日 令和8年度より「子ども・子育て支援金制度」が始まります
- 2025年11月13日 国民健康保険は健康を守る助け合いの制度です
- 2025年11月6日 12月は国民健康保険制度の適用適正化月間です